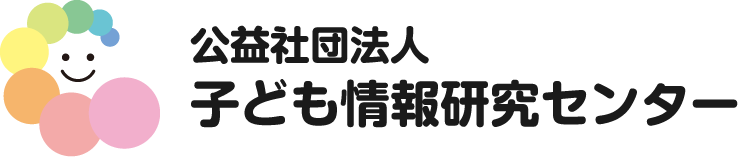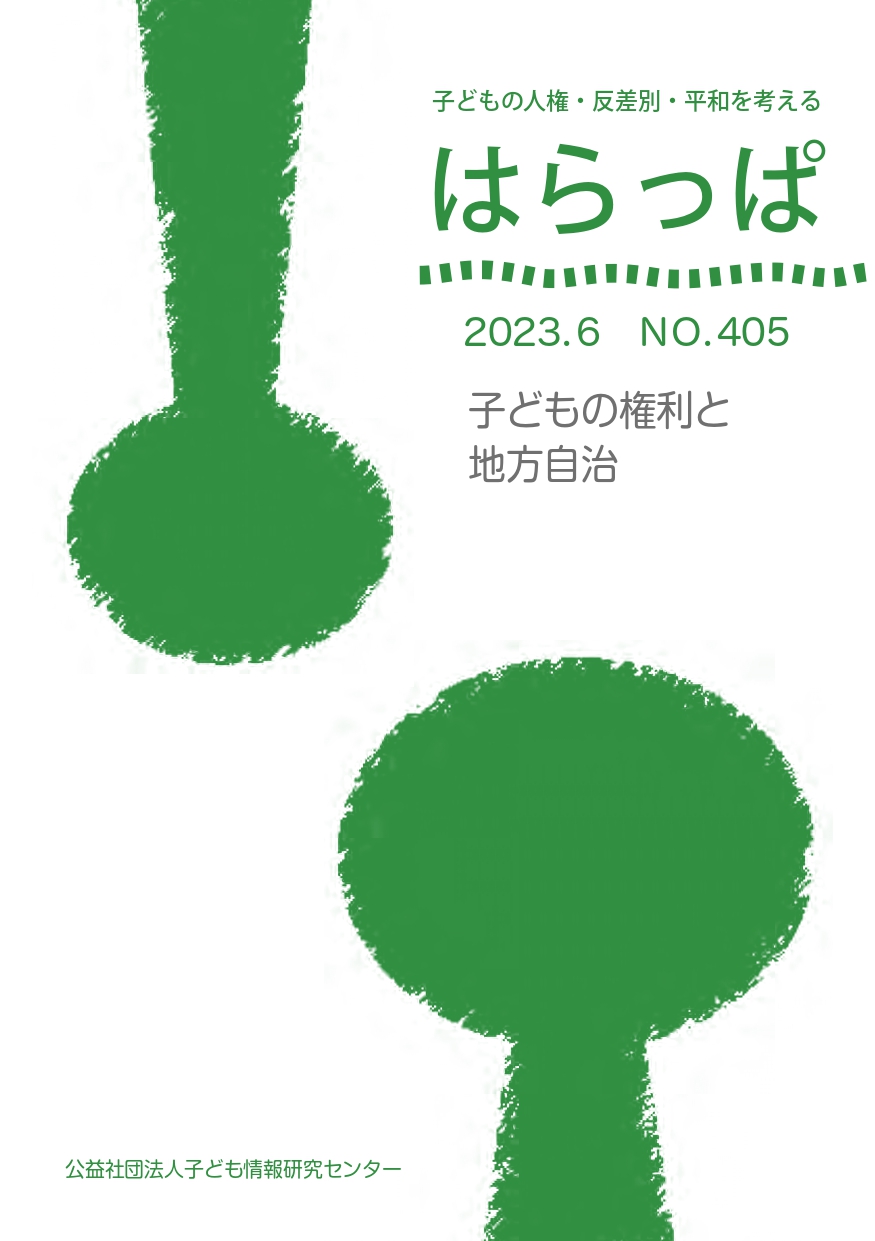出版物・研究一覧丨子どもに纏わる研究
-
はらっぱ
◆子どもと地方自治~こども基本法を活かす子ども条例を~/吉永省三◆“インクルーシブ”をキーワードに私が地域で取り組んできたこと/佐々木サミュエルズ純子◆学校に行かずに育った娘たちとの日々から見えてきたもの/一海真紀◆子どもの学びの声を聴き、子どもとともに学びを創ろう/藤田美保
-
はらっぱ
『はらっぱ』2023年3月号 特集:インクルーシブ教育への議論をひろげよう
インクルーシブ教育を考える重要な視点 ~国連主義を超えて~/桜井智恵子不登校から考えるインクルージョン/山下耕平みんなでともに ~インクルーシブ教育の現場で見えた可能性と難しさ~/藤本まどか生まれて、生活していること自体を否定する日本という国/川本朋子<座談会> 子ども会議のような学校をつくりたい/浅羽大地・直川宥澄・野中唯名
-
はらっぱ
そもそも「憲法」とは何か?~その歴史や今日的意味~/伊藤真 再確認すべき憲法24条の価値と相反する動き~家父長的ジェンダー規範からの克服を求めて~/清末愛砂 主権者意識はどのように育つか?/肥下彰男 憲法と私~憲法は盾、使いこなしてこそ人権は守られる~/森松明希子
-
はらっぱ
『はらっぱ』2022年9月号 特集:今改めて「子どもの声をきく」を問う
「子どもの声を聴く」意味 ~名古屋市子どもの権利相談室「なごもっか」の活動から~/谷口由希子子どもに届く「子どもアドボカシー」/奥村仁美「子どもの話をきく」という実践 ~子どもオンブズワークの探求の中で~/森澤範子物語を読むように、きく/多田頼子
-
はらっぱ
『はらっぱ』2022年6月号 特集:「子育て不安」の根っこを考える
労働の意味について考える ~「資本の経済」「国家の経済」、そして「生活の経済」~/田畑 稔“ケア”と“仕事”が両立できる「働き方改革」を/禿あや美ワーカーズコレクティブの挑戦/白江祐子「能力主義」を乗り越える視座 ~「子育て不安」という言説から考える~/吉永省三
-
はらっぱ
『はらっぱ』2022年3月号 特集:「市民自治の力を引き継ぐ」
座談会 市民自治の継承/奥村仁美・窪田 勉・西尾慧吾・山田 潤 インタビュー 自分が精一杯生きること・叫ぶこと/語り手 永久睦子・聞き手 西尾慧吾・寄稿 わたしと政治/湊 隆介・市田康美・ 久保有美・大椿ゆうこ
-
はらっぱ
『はらっぱ』2021年12月号 特集:『コロナ下、「戦争」を考える』
パンデミックと移動の自由~「越境」「接触」「対話」がつくる広場の学び~/吉見俊哉・子どもの意見表明・参加の権利と“三分の一配分” への権利~子どもの権利思想の探求者 J.コルチャックに学ぶ~/塚本智宏・差別を許さない社会をつくる~子どもたちとの約束~/崔江以子おんなたちは尊重の花を植える~宮古島からミサイル基地が撤去される日を夢見て~/石嶺香織・「遺骨土砂問題」意見書運動~「市民と野党の共闘」を探る~/西尾慧吾
-
はらっぱ
これからの街づくりで大切なこと ~釜ヶ崎からこそ見える~/生田武志・公教育をわたしたちの手に取り戻す闘いを! ~学ぶ権利の主体は子ども~/久保 敬・今ここで生きることを楽しむ放課後/渡邊充佳・つながりあってつくる わたしたちのまちの医療/永久教子・差別を乗り越え、道を切り拓いていく/友永健吾
-
はらっぱ
はらっぱ2021年6月号 特集:『福島原発事故から何を学ぶか?』
原発事故から10年 福島の今/武藤類子・子どもの内部被ばくを減らす食生活/安田節子・幼稚園留学/林 リエ・原発労働 理不尽の根っこをみつめる/寺尾紗穂・原発事故をどう伝えるか ~文部科学省放射線副読本の課題~/後藤 忍
-
はらっぱ
はらっぱ2021年3月号 特集:『東日本大震災10年と子ども』
10年目の校庭で/佐藤敏郎・放射能から避難する権利 ――原発避難者の10年――/森松明希子・子どもが企画デザインした児童館 らいつ/吉川恭平・「自分たちのふつうの居場所を 地域でつくる」を支える/谷川由起子